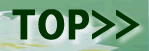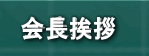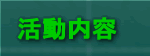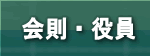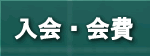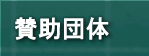½¬25N1124úiújAéʧÛHº¤ï@æWñÇá¢ïªJóêAãtEÈãtðͶßÅìtAÈq¶mA¾ê®omAÇh{mâîì{ÝEõPOU¼ªQÁµ½B
ͶßÉAOñuïÌQÁÒ©çñ¹ç꽿â̤¿AQÂÌáÉ¢ÄÇᢪsíêA»ÌãRe[^[yÑQÁÒÉæéfBXJbVªsíê½B
±¢Äã¼ÍAutÉÐï@l¼I@îÒ{Ý⵨@Íû^¢Çh{mð}¦AuH×é±Ævðx¦éA{ÝÅÌæègÝ`⵨ÌHPAÆrPAÉ¢Ä`Æèµu𢽾¢½B
ïêOÌzCGÅÍAÖAÆÒSÐÉæéûoPAObYâºHÈÇÌW¦àsíêA¡ñà巵̤¿ÉÂïÆÈÁ½B
Çá¢
Çá¢ïÌO¼ÍAOñÌuïQÁÒ©çñ¹ç꽿â̤¿AQÂÌáÉ¢Ä{¤ïÌån걪À·ð±ßÇᢪsíê½B
ܸáPƵÄAunæ§
^Á{оÜèÌëÞ³µÌvVäKqÅìt©çÌH`ÔÉÖ·é¿âi79Î@j«@»ÝÌóµFFmǪ èAét]C¡ÉÈèAHÌÌÝoÁµÄ¢éóµBHÌÞ¹ªÈOæè½ÈÁÄ«Ä¢éB»ÝÌYݲÆFH`Ôðl¦éÛÉAíH¨«´Ý¨~LT[Æ¢¤æ¤É`ÔðÆ·©Ç¤©BùÝÝAÞ¹ÌL³ÈOÉÇÌæ¤È_ðÏ@µ½çæ¢Ì©À¤ª éBwWðmè½¢Bj
áQƵÄAußnæïxZ^[yMvRú±¨qÅìt©çÌJûÉÖ·é¿âi¢ÁÄ¢éAYñÅ¢é±ÆFFmÇÌûÅAJûµÄêÈ©Á½èAûÌÉHרªüÁÄàÈ©È©ð^®ªnÜçÈ¢½ßÉHÉÔª©©ÁĵܤBêÎêÅêl¾¯ÉÔð©¯é̪ïµAÇrÅâß´éð¾ÈÈéBÔð©¯Äà{lªæêÄAÅãÉZÝAëµÄµÜ¤±Æà éBJûð£·hÌ|Cgâð^®âº^®ðU·éRcÈǪ Á½ç³¦ÄÙµ¢BܽîÌPñÊÉâè è©BëãÌzøðl¦Ay[XgHɵĢé̪âèÈÌ©Bð©çº^®Éißé|CgÍ éÌ©Bj
áPÉεAãţê©ç{¤ïÌåORIYA¾ê®om̧ê©ç{¤ïÌ´
[qÉæéN`[ªsÈíê½B
åORIYÍAÇÌæ¤Éº²®HðIð·é©É¢ÄAÛHóµÌxͯ¶ÅàAºáQÌaÔͯ¶ÅÈ¢BÇáÉæÁÄáQÌü¢Ä¢éRÂÌxNgûüiðÍ·Èí¿ÝÓ«HòƵÄÜÆßé\ÍBº½ËÌäN«·Èí¿^C~OæÛÝßé©Ç¤©BôªNAX·Èí¿c¯ÈH¹Éè±ßé©Ç¤©jðáÉñ¾H`ÔðIðµÈ¢Æ¤Üs©È¢BRÂÌxNgûüðl¦Èªçº²®Hðl¦Ä¢½¾«½¢Æq×½Bi}PQÆj
ú{ÛHEºnwïwïªÞiQOPRjÌuº²®HÌIðis~bhjvªQlÉÈéÌÅ¥ñú{ÛHEºnwïgoihttp://www.jsdr.or.jp/jðQƳ꽢B
´
[qÍAÁÉFmÇÉηéÀSÈÛH̽ßÉåØȱÆƵÄAoÁAÓ¯ªµÁ©èµÄ¢é±ÆBHð·é±ÆªÓ¯Å«AH×éÆ«ÍÚªoßÄ¢é±ÆBÄzíÖWÌóµªæ¢±ÆBp¨ÌÀèªæ¢±ÆiÇ¢ððÝè·éjB£§Ì`ÔªA@\ÉÁÄ¢é±ÆBêûÌÊâH×éy[XªRg[Å«é±ÆB뵩¯ÄàAPŵÁ©èo¹é±ÆBð°AHOÌõ ƵÄASgÌóÔð®¦é±ÆB
·Èí¿AûoàÌq¶oÁÌmFAüãAHðnßéÓ¯t¯AÀSp¨ðÆé±Æi¤ª¢Eûo´@EHOÌEÓÌmFEZbeBOÌmFjÅAî{IÉåØȱÆÍwp¨ÌHvixXg|WVð©Â¯éjxÆྵ½BܽFmÇÖÌïÌIÈÎƵÄAH¨ÌFmáQAÓªWÅ«È¢AôªÖÌèÝÌ^®ªJnÅ«È¢AÇÌæ¤ÉùÝñÅ梩í©çÈ¢A¤ÂXüÅH׽ȢAHAE}§A©«ÌáºAÉεA¢ºáQ|Pbg}j
AæRÅ@ãòoÅQOPPðøpµÄྵ½B
±¢ÄáQÉεAÈãţê©ç{¤ïÌ¢`AÈq¶m̧ê©çéʧÈq¶mïÌåvÛì¨qê±ÉæéN`[ªsíê½B
¢`ÍAuJû¢ïÇáÖÌÎvƵÄAE´ìÌdûièjAj|Cgh@i}QQÆjÉ¢ÄڵྵAXÉÁ¼ÆÛ¼Ìdv«ÉGêAíXÌJûíÉ¢ÄàÐîµ½B³ÒÍpÒª¢©ÉÓ¯ªÈ¢Æ´¶Ä¢ÄàAÇñÈàsשÌÉ¢ÄðµÄ¢é͸B^SðÁÄsµÄ¢¯ÎAK¸â\îÉ\êÄéBèÌÊàèâ«æÌ·xAJ¢Ä¢êÎáÌ®«âÜν«·çàÇÝæêé͸BlªlÅ é±ÆðYêÈ¢±ÆAÆñ¾B
åvÛì¨qÈq¶mÍAFm@\áºÉæéûðJ©È¢±ÆÖÌÎôƵÄA
¤uHðF¯Å«È¢vÉ¢ÄÍAßHÌ£µâèwièéÝjAHרALoA¡o©çÌ´oüÍâèÉXv[ð½¹ÄûÖ^ιA±êÜÅÌo±ðv¢o³¹éB
¤u´n½ËÌo»vÉ¢ÄÍAÞ^C~OÅÌßHîâHïÌHvÅ éB
¤ûÍ殢ĢéÌÉA¢ÂÜÅàûÌÉcÁÄ¢é±ÆÖÌÎôƵÄÌAuôªÖÌÚsSvÉ¢ÄÍA¬®«Ì éÚªeÕÈHiÌñâAêûÊÌl¶âº^®ðmFµÄ©çÌîðs¤±ÆâAº½ËäN̽ßÌPûiACX}bT[WA÷}bT[WjÅ éB
¤ßÝÖÌÎôƵÄÌAuHרªF¯Å«È¢vÉ¢ÄÍAâàÌâh¢àÌÈÇA¾mÈ¡ðÁ½HiÖÌÏXâAºÌ£µâAèwH×âALoA¡o©çÌ´oüÍÆྵ½BºPû@É¢ÄAAÌACX}bT[WA§±ç¦ºAªãPûA ººPû@Af\èZû@iAªqbóîrÉèðÄSNÆóºðs¢AÅàãµ½Êuŧð~ßÄÛjAºÌðྵ½B
ܽAûoPAÉpµÄ¢éÛ¼ÜðÐîµ½BÅãÉAÈq¶mªÛHÉÖíéL[p[\ÉÈé±ÆðÚwµÄ¢éÆñ¾B
ÅãÉARe[^[iãţê©çåO{ïAÈãţê©ç¢{ïA¾ê®om̧ê©ç´
{ïAÅìţê©çxq{ïA¨æÑéʧ§zÂíÄzíaZ^[}´óüÛHEºáQÅìFèÅìtAÈq¶m̧ê©ç§q¶mïåvÛê±Aã¼ÌuïutÌÐï@l¼IîÒ{Ý⵨ Íû^¢Çh{mjÉæéAfBXJbVªsíê½B
}´óüÅìtæèA¢FmÇÌûXÉÍA±êÆ¢¤«Á©¯ª ê뱩çißçêéÆ¢¤±ÆðÀ´µÄ¢éB¢ë¢ëÝÄÝé±ÆªÌvÅ éBv
xq{ïæèA¢FmÇÌûXÖÌKâÅìɨ¢ÄA`[àÅÌÛHóµAºóµÌîñ`Bð§És¢Aîñ̤Lð}é׫ŠéBܽR~
jP[VÌdv«ðÉ´µÄ¢éBv
Íû^¢Çh{mæèA¢h{mƵÄA²®Hð¢Â௶`ÔAóµÅñ·éÉÍð¢Å¢éB±ÌãÌÌuàeð©ªÌ{ÝÆä×ÄAQlÉÈé_Í{ÝÌh{mÉ`¦ÄÝÄ¢½¾«½¢Bv
åO{ïæèA¢AgµÄ¢éeEíÔÅA»êÉÖíêéÔIÈ]Tɧñª éB»Ì½ßÉåȱÆÍÆ°ðæè±Þ±ÆÅAóµAîñðÆ°É`¦ÖðL°Ä¢«½¢B£
ïê©çA¢ÝîÉÖíÁÄ¢éªA½EíAgƵÄÈq¶mƼÚb·@ïªÈ¢£ÆÌÓ©ªñ¹çê½B
| u@ |
uH×é±Ævðx¦éA{ÝÅÌæègÝ
`⵨ÌHPAÆrPAÉ¢Ä` |
| ut@ |
Ðï@l¼IîÒ{Ý⵨
Çh{m@Íû^¢æ¶ |
ã¼ÌuïÍAutðÐï@l¼IîÒ{Ý⵨ÌÍû^¢Çh{mɨ袵½BèÍuH×é±Ævðx¦éA{ÝÅÌæègÝ`⵨ÌHPAÆrPAÉ¢Ä`Å éB
⵨ÍüÒ80¼ÅîìxͽÏSE01A½ÏNîª82EUÎAjäÍPFRų|IÉ«ª½AH`ÔÍoÇh{R¼ð«74¼ªoûÛæÅ éBHÌPAͼEíŪSµîìAã±Ah{̪ìŦ͵ĢéBh{`[ÌÖíèÍÛHºáQEð¢ïÈûXÖÌðEº²®HÌñAæèæ¢H`ÔÌHvðpÒâîÒ©ç·«æÁÄüPA©HíÌgpâh{âHiÅs«ªðâÁ½èµÄ¢éB
ÌsÅo³êé¨ÙÍíH¾¯ÅÈÛHºáQÌ éûÉàyµñÅ¢½¾¯éæ¤HvµÄ¢éBüÒÌH×ûÌÏ@ðµÈªçA¨¢µÀSÉH×çêé¿ìèðsÁÄ¢éBPÉHðñ·é¾¯ÅÈAÌdâSgóÔðÏ@µAáh{óÔÉ×çÈ¢æ¤Éh{}lWgÉæègñÅ¢éB©ÞÍAùÝÞÍÌẵ½ûÉÍAH×â·iðºjÁ»µâ·¢`Ôɵ½âíç©HðñµÄ¢éBâíç©HÆÍ¿iHÞjð~LT[É©¯Q»ÜÅÅß½àÌÅAãÆã ²ÅÂÔ¹éųÅAÌݱÝÕ¢Èß穳ðÁ½HÅ éB
»Ì¢Â©Ì²áðXChÅñ¦µ½ªAH×éÆ¢¤±ÆÌî{ªAÛHºÌTúÉ éÆl¦ÄÀÛÉ»êEõÖÌAP[gÈÇðîÉâíç©H𮬵½B»ÌTOÍAãÅÂÔ¹AÜÆÜèª ÁÄA©½ÚÉÇAùÝÝⷢƢ¤ðªõíÁÄ¢é±ÆB»µÄNªÇÌæ¤È`ÔÅH×é©ÍîìEªSÉßÄ¢éBåHͲÍñEE[[E~LT[A¨©¸ÍíHEêûåE«´ÝHEâíç©H©çIñÅàç¤BîìHÖÌæègÝƵÄJÌÆëݲ®Üâ[`E¦VÈÇÌgp©ç½x©ÌüPðoĽ¬QPN©çÍâíç©HÉæègÝnß½B
@ï é²ÆÉoãªÁ½¿ðEõÉHµÄàç¢A´¿ª¯¶¿ðH`ÔðϦé±ÆÅðµâ·ùÝÝâ·¢¨ÉϦÄsÁ½BܽǤµÄàs«ª¿Èh{ÉÖµÄÍsÌÌâHiÌpª¢³ê½BêûÅHîÌÛÉg¢â·¢HíÌüPâHíÌFâ`AzuÜÅࢵ\ªÈ¬Êðã°é±ÆªÅ«½B
yH×é±ÆÆo·±Æz
rÌÖA«ð¢µ»êÜÅòÜÉæérÖRg[ÉæÁÄÖéƺðJèԵī½±Æð½ÈµA{ÝàÉurPAðl¦éïvð§¿ã°ÄæègÞ±ÆÉÈÁ½BEõÔ̤ÊÌF¯ðßé½ßÉAuXgrÖXP[Æ¢¤\ðÌpµÄA±êÉæèüÒÌróµðc¬·é±ÆªÅ«½B
»ÌÊAºÜð~µH¨@Ûð
ªÆÆàÉæèüêé±ÆÉæèRNÔÅòÜÌíÞÉæÁÄÍO©Ü½Í½ÌP[XÅgppxª¸µ½B»µÄ»êÜŽ©Á½
lÖâDóÖª10ÉÈèA½ªÊÌÖÉÈÁ½B
±±ÅÌh{`[ÌÖíèÍ
ªÛæÉÛæµÄàç¤H¨@ÛðIèAêlêlÌ
ªÚÀÊÌvZA¨¢µÀSÅH×â·¢HÌñAÛHº]¿ÉKµ½Hðñ·é±ÆÅ éBܽAº@\Ìẵ½ûÉ[`[[â¦V[[ðñµA
ªðÛæµÄ¢½¾¢Ä¢éB¨¢µ¢HÆÍîÒÌẵĢé¡oÉηéæ¤É|ÝðÁ¦½èXpCXðp¢½HBFÇèªÇAH´ªÇA©½Úªü¡µ»¤É·èt¯çê½HAÆ¢¤±ÆÉÈéBêûÅH×â·¢HÆÍu©ÞEùÝޱƪeÕÈûvÅÍ´íèàü¡µ³Ì¤¿ÅAu©Þͪẵ½ûvÅÍ×·éÌÅÍÈâíç©·éBuùÝݪẵ½ûvÅÍHרÉÜÆÜèª èAèâ·¢±ÆªðÉÈéBÅãÜÅpÒÉû©ç¢µãªÁÄ¢½¾½ßÉAø«±«KØÈHxðsÁÄ¢«½¢ÆèÁÄ¢éB
¡ãÍnæÌ{ÝEa@ÔÅàH̤ʾê𿽢Æl¦Ä¢éB |